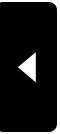2007年07月19日
土壁を付ける 1
台風も無事に通り過ぎて、いよいよ現場では土壁を付ける作業が始まりました。早朝に中主町にある建材屋さんからダンプカーで土壁を運び込みポンプを使って土を二階まで送ります。

左官屋さんが竹下地に土を付けて行きます。しっかりと押し付けることで竹下地の裏側まで土が押し出されしっかりした壁になります。次の工程は乾き具合を見計らって裏側にも土を付けます。

天気が安定することを願いながらの土壁の作業風景です。

21日(土)に土壁の見学と「木の家の安全性と耐震性」についての講座を開きます。
左官屋さんが竹下地に土を付けて行きます。しっかりと押し付けることで竹下地の裏側まで土が押し出されしっかりした壁になります。次の工程は乾き具合を見計らって裏側にも土を付けます。
天気が安定することを願いながらの土壁の作業風景です。
21日(土)に土壁の見学と「木の家の安全性と耐震性」についての講座を開きます。
2007年06月29日
現場レポート(屋根と壁の納まり)
棟木を納めることを上棟(建前)と呼んで、関係者が寄ってお祝いを開きます。古くは木材が貴重な資源であった時代は家を建てる建築材、橋や川の堤防など土木資材、薪として燃料、お箸や親碗やお盆など什器、家具や荷車などの道具としてなど本当に生活に密着した大切な資源だった。その大切な木を使った家を建てることは、家族や親戚そして地域の人々も巻き込んで喜べた祝い事だったようです。
現在の住まいには、木を使い丈夫な骨組みをつくることと、断熱や気密のような性能を上げることが必要です。そのために屋根面には、杉板の30㎜厚を張り、その上に断熱材50㎜(ネオマホーム)を敷き込みをしています。写真

断熱材の上に通気性のあるシート(タイベック)を張りそして通気層20㎜を取りその上に野地板12㎜を張って屋根材(ガルバリューム鋼鈑)の施工になります。これでバッチリ断熱効果あり!
壁は土を付けるので柱から柱まで横に貫を三段通してクサビで止めています。写真

そして竹で下地を組んでゆきます。竹小舞下地ここに土を付けます。写真

竹で組んだ下地は土の中に入り腐らずに永く建物を土と木と共に支ええてくれます。明日30日は現地で見学会と説明会を開催していますので見に来て下さい。 TOKU
現在の住まいには、木を使い丈夫な骨組みをつくることと、断熱や気密のような性能を上げることが必要です。そのために屋根面には、杉板の30㎜厚を張り、その上に断熱材50㎜(ネオマホーム)を敷き込みをしています。写真
断熱材の上に通気性のあるシート(タイベック)を張りそして通気層20㎜を取りその上に野地板12㎜を張って屋根材(ガルバリューム鋼鈑)の施工になります。これでバッチリ断熱効果あり!
壁は土を付けるので柱から柱まで横に貫を三段通してクサビで止めています。写真
そして竹で下地を組んでゆきます。竹小舞下地ここに土を付けます。写真
竹で組んだ下地は土の中に入り腐らずに永く建物を土と木と共に支ええてくれます。明日30日は現地で見学会と説明会を開催していますので見に来て下さい。 TOKU
2007年06月27日
現場リポート<上棟編>
先週、梅雨の合間をぬってとうとう棟が上がりました。
ちょうどお施主さんの子供さんが小学校から帰ってきた時に棟に取り掛かった
ので大工さんたちと一緒に「そーれ!そーれ!」拍手喝采。

その後、何本もある垂木を並べて作業を終了しました。
日が暮れる前に粗方片付けを済ませ、上棟式が始まります。
建物の1階で御幣に向かって、2礼2拍手1礼し、建物の隅を酒、塩、洗い米で
清めます。
そして、お施主さんと施工者、設計者が一緒に席について乾杯です。

日も長くなり、夕暮れの楽しいひと時を過ごさせていただきました。
いちかわ
ちょうどお施主さんの子供さんが小学校から帰ってきた時に棟に取り掛かった
ので大工さんたちと一緒に「そーれ!そーれ!」拍手喝采。
その後、何本もある垂木を並べて作業を終了しました。
日が暮れる前に粗方片付けを済ませ、上棟式が始まります。
建物の1階で御幣に向かって、2礼2拍手1礼し、建物の隅を酒、塩、洗い米で
清めます。
そして、お施主さんと施工者、設計者が一緒に席について乾杯です。
日も長くなり、夕暮れの楽しいひと時を過ごさせていただきました。
いちかわ
2007年06月23日
現場レポート(土台~建て方)
基礎が出来上がり次は建物の土台を据え付ける作業を行います。土台は腐りにくく強い国産桧材の芯持ち材を使い、基礎のコンクリートと直接接しないように栗材のパッキンをかましてシロアリ対策をしています。また主要な柱は基礎からボルト(写真中央部 複雑に加工した土台の仕口に柱が噛合う)で浮き上り防止を施しています。

加工場で大工が刻みした柱や梁の材を板図の符号(イロハニ・・・一二三・・・)順に手際よく組み立ててゆきます。
 板図
板図
 刻みした材 仕口に符号が見える
刻みした材 仕口に符号が見える
そして現場で建て方

二階の床組みができました 大梁と小梁が組み上がった!

次の土曜日(30日)に木組みの見学会を開催しますので見学にお越し下さい。
TOKUさん
加工場で大工が刻みした柱や梁の材を板図の符号(イロハニ・・・一二三・・・)順に手際よく組み立ててゆきます。
そして現場で建て方
二階の床組みができました 大梁と小梁が組み上がった!
次の土曜日(30日)に木組みの見学会を開催しますので見学にお越し下さい。
TOKUさん
2007年06月07日
現場レポート<基礎編>
午後から基礎のベース(一番底の部分)のコンクリートを打つので、鉄筋の施工状況を確認してきました。

基礎は建物の下全体に鉄筋を配し、コンクリートを打つベタ基礎です。
その下には地盤からの湿気を遮断する防湿シートを敷いています。
指定のサイズの鉄筋が指定の間隔で配置され、しっかりと結束されているかどうか
施工者とは違う設計者としての目で確認することも大切です。
アンカーボルトの設置等細部の確認も必要です。
立ち上がり部分のコンクリートを打つ時には、型枠と鉄筋が充分な間隔を保っているかどうか等、もう一度確認に行きます。
基礎は建物の下全体に鉄筋を配し、コンクリートを打つベタ基礎です。
その下には地盤からの湿気を遮断する防湿シートを敷いています。
指定のサイズの鉄筋が指定の間隔で配置され、しっかりと結束されているかどうか
施工者とは違う設計者としての目で確認することも大切です。
アンカーボルトの設置等細部の確認も必要です。
立ち上がり部分のコンクリートを打つ時には、型枠と鉄筋が充分な間隔を保っているかどうか等、もう一度確認に行きます。